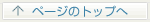健康のために身体を動かす、スポーツを楽しむ、身体を鍛える・・・
みなさん、それぞれに目的を持って運動をされているかと思います。
ここでは、日常生活に取り入れると快適に過ごして頂けるような、簡単に出来るストレッチや身体を引き締めるトレーニング方法、またスポーツをされる方には是非知って老いて頂きたい応急処置などを紹介していきます。
ぜひ一度目を通してみて下さい。
運動と健康についてのお話
スポーツをされる方に知っておいて頂きたいこと
なぜ治療が必要なのか?

身体のメンテナンスとパフォーマンスの向上
技術の向上を考えるなら、しっかり身体をメンテナンスしましょう。
なぜなら『痛み』が身体の動きを制限するからです。
一生懸命多くの練習をしても思うような結果が出ないことがあります。
それは身体のバランスの崩れにより、あなたの理想の動きが出来なくなっていると考えられます。
ですから治療を施すことで、『痛みのないバランスの整った状態』にしてパフォーマンスの向上を目指しましょう。
私が治療家になった理由
私は高校生時代ハンマー投げの選手としてインターハイに出場しました。
しかし、無理なトレーニングの積み重ねと悪い身体のコンディションのまま、練習を続けた結果、重度の腰椎椎間板ヘルニアとなり、選手として一番大事な時期をベッドの上で過ごすことになってしまいました。
ですから、成長期の中学・高校生のスポーツ選手の方々には、ただ根性のみで練習をするのではなく、しっかりとした科学的なトレーニングと治療が必要だと思っています。
もしも今、自分が伸び悩んでいたり、痛いところがあるのであればぜひとも治療を受けてください。
そうすればパフォーマンスも変わり、結果も変わってくると思います。
障害を抱えたまま生活をしているスポーツ選手も多くいますが、そうならないためにも早くからの治療が一番大切だと思います。
健康な身体と健康な心
パーソナルトレーナーとしてもプロスポーツ選手のトレーニング指導を行っています。
一流の選手に提供するものは一流のものでないといけません。
ですから常に学び成長を心がけ生活するようにしています。
これからは、多くの方々、学生さんたちにまつもと鍼灸整骨院を知っていただき、皆さんの競技能力を上げるためにしっかり施術をしていきたいと思います。
健康な身体、健康な心。これを持つことにより楽しい生活があるのではないでしょうか?
身体と心作りの為のお手伝いをしていきます。
![]()
ウォーミングアップの必要性 ~突然のケガを防ぐために~
柔軟性ストレッチを運動前のウォーミングアップとしてを行っている選手やチームが多くみられますが、実際運動時にはその効果は薄いものです。
なぜなら、ストレッチのみでは身体の深部温(体温)が上がらないからです。
柔軟性ストレッチはウォーミングアップの方法として用いられるものではなく、ジョギングなどでしっかり汗ばむ程度まで体温を上昇させた後に行うべきものです。
ウォームアップは筋温を上昇させる活動であり、活発な運動を行うための身体的準備となります。
1)ウォームアップ後の体温上昇による効果
・筋への血流量の増加 ・神経伝達速度の向上 ・柔軟性の向上
2)ウォームアップなしでの柔軟性ストレッチの効果
・筋の収縮、伸長が少なく摩擦が生じない
・筋温が上がらず、体温の上昇もわずかである
・筋温の血管拡張の反応に影響を及ぼさない
3)ウォームアップの種類
一般的なウォームアップとしては「ジョギング」「縄跳び」「サイクリング」等があり、大筋群の動作による基本的な活動が適しています。
心拍数、筋の深部温(筋温)、呼吸数、関節液のの粘性を高め、血流や発汗を促進します。
筋温の上昇は柔軟性を高め、それが身体を動かすための準備になります。
筋温を上げる方法として「シャワー」や「ホットパック」「マッサージ」などがありますが、これらは筋温を上げる目的では効果的かもしれませんが、活発な身体活動に対する準備が目的である場合はお勧めすることは出来ません。
4)ウォームアップの手順
ウォームアップの手順は、1.ジョギング、2.ダッシュ、3.ジャンプ などを行い軽く汗をかきます。
ジョギングとダッシュの間に軽く反動をつけたストレッチや運動をすると良いでしょう。
但し、反動をつけることによって今までに痛めていた場所が強く痛むことがあるのでご注意ください。
痛みが出る動作は、身体の動きを無意識に制限し、パフォーマンスの低下にもつながります。
より楽しく、より快適にスポーツを行うのであれば、身体のケアはしっかりと行いましょう。
![]()
RICES処置について ~もしケガをしてしまったら~
PICES処置とは

付き指、肉離れ、捻挫、骨折、打撲など、ほとんどのケガの場合は痛み・内出血や腫れが生じますが、これらを最低限にとどめ、損傷期間を短縮するための処置です。
Rest(安静)、Ice(冷却)、Compression(圧迫)、Elevation(挙上)、Stabilization(固定)を意味します。
(1)Rest=安静
ケガをした部分はむやみに動かしてはいけません。
ケガが悪化しないように安静な状態に保つことが大切です。
(2)Ice=冷却
炎症を抑え、内出血を最小限に抑えるためには、受傷直後にアイシングを行うと効果的です。
アイシングを直後に行うことで、通常受傷後4~6時間後に発生する滲出物をも減少させることが出来ます。
また同時に痛みや内出血、腫れを軽減してくれます。
しかし注意しないといけないのは長時間のアイシングは組織の損傷を引き起こす原因になります。
そのため、アイシングは約20分間行い、起きている時間中1~1.5時間おきに繰り返します。
アイシングを行うことで炎症反応を抑制し、外傷の回復は促進されます。
この段階で適切な処置を行っておけば外傷による損失時間は短縮されます。
※アイシング時の注意点 ~凍傷に注意しましょう!~
凍傷は基本的に0℃以下で起こります。
氷のうや氷袋でのアイシングは凍傷になりにくく、長時間冷やしても問題はありませんが、クライオバックや冷却パックを直接肌にあてて長時間冷やすと、凍傷になる可能性が高くなりますので、使用する場合は必ずタオルなどで包んで使用してください。
(3)Compression=圧迫
アイシングと同様、内出血を防ぐために行い、アイシングと同時に行うとより効果的です。
しかし、圧迫が強すぎると血液の循環が悪くなるので注意が必要です。
圧迫後は患部より先がしびれたり、色が変わっていないかを確認し、症状が見られれば圧迫を弱めます。
(4)Elevation=挙上
ケガをした部分には血液が溜まりやすいため、患部が腫れやすくなります。
冷却、圧迫処置をした患部を心臓より高い位置に上げて、出血、内出血、腫れを軽減させます。
手首、足首が患部なら仰向けに寝た状態で患部の下に座布団などを2枚程度重ねて敷くと良いでしょう。
また睡眠中の挙上は5~6cm上げておけば可能です。
(5)Stabilization=固定
固定は圧迫と同時に行います。
痛めた筋肉や関節を動かさないために固定し、悪化を防ぎます。
※以上は運動直後に受傷した場合の応急処置です。 |
健康ストレッチ教室正しくストレッチが出来ていますか?
日常生活にストレッチを取り入れましょう

普段の生活やスポーツ・仕事などによる疲労の蓄積から起こる、肩こりや腰痛などを予防・改善するために「毎日のストレッチ」を行いましょう。
ストレッチは筋肉や関節の柔軟性をアップさせ、過剰に高まった筋緊張をとることで、筋肉痛の予防や筋・関節の障害を予防し、また身体や精神に対するストレスを取り除くのに有効であるといわれています。
しかしながら、間違った方法では本来の柔軟性をアップさせるという目的とは反対に筋肉や靭帯をかえって傷つけてしまう場合もあります。
『健康ストレッチ教室』では、筋肉や関節の柔軟性をアップさせ、軽い痛みや凝りを和らげることを目的とした簡単なストレッチの正しいやり方や、ポイント・注意点を解りやすく説明しながら紹介していきます。
|
首のストレッチ頸部(前・横)・僧帽筋



首の横、後ろの筋のストレッチは手で頭を押さえ、写真の様に前・横・斜めなど気持ちの良い方向へとゆっくり伸ばしていきます。
首の前側を伸ばすには胸に手を当て、同じようにゆっくりと頭を後ろへ倒していきます。
ストレッチした時に手にしびれが出ない様、慎重に無理せず伸ばしていきましょう。
デスクワークやPC作業が長時間続くと、首周辺の筋肉が固くなり、頭痛や肩こりの原因となります。
お仕事中に疲れを感じた時に、ほんの数分で良いのでストレッチをやってみてください。
腕のストレッチ前腕部・上腕部
 1
1  2
2
1)ポイントは肘を完全に伸ばしきることと、抑える手の位置は肘よりも肩側にします。
肩関節の横・前・後ろ・肩甲骨までストレッチされている感じがあればGOODです。
2)のポイントはしっかりと肘を押さえることと、体が曲がらないように真っすぐにすることです。
体が横に倒れてしまうと、背中の筋肉も伸びてしまい、腕の筋肉に負荷がかからない為、しっかりと腕の筋肉が
伸びて、体が曲がらないように意識してやってみてください。
 3
3  4
4
3,4)ポイントはしっかりと肘を完全に伸ばしきることと、反対の手の位置は指でなく、手のひら・手の甲を持って前腕の筋肉をストレッチします。
体幹のストレッチ大胸筋・広背筋・大腰筋・起立筋
 1
1  2
2
大胸筋をはじめとする胸の筋肉を伸ばすストレッチです。
胸周辺の筋肉が硬くなると、肩が前に入り猫背姿勢になりやすく肩こりや腰痛の原因となります。
ポイントは肩と肘の角度を90°にすることと、ストレッチしている側の足を一歩後ろに引くことです。こうすることで、より胸の前の筋が伸ばされやすくなります。肩甲骨を背中側に引くようにするとより伸びる感じが得られると思います。
 3
3
3)のストレッチはまず肩幅に足を開き、ストレッチする側の手を反対の体の前に出します。
そのまま逆の手で、斜め前や横など気持ちの良い方へと引っ張るようにします。この時、引っ張られている手は脱力しておいてください。次にストレッチされている側の足を一歩後ろに引きます。そして股関節かひざ関節は曲げて良いので後ろに重心を移動させます。手で前方へ引っ張り、お尻は後ろに引く様にすることで脇腹から背中、腰まで伸ばされる感じが出ると思います。荷物を持ったりすることが多い方は脇腹・背中・腰なども硬くなりやすく、腰痛などの原因となるのでぜひやってみてください。
 4
4
4)腸腰(ちょうよう)筋という筋肉のストレッチです。
ポイントはおなかに力を入れ、腰が反らないように注意することです。おなかの力をキープした状態でストレッチされている側の股関節を前に突き出すようにすると、より伸びる感じが得られると思います。
 5
5  6
6
5)首から腰までの背中広範囲を伸ばす筋肉のストレッチです。
ここが硬くなると腰はもちろん首の動きも悪くなってしまいます。
体の正面に両手で大きな輪っかを作り背中を丸くしていきます。この状態で輪っかを上下に動かす(6)ことで伸ばされる場所が変わっていきます。特に硬くなっているところを重点的に行って全体的に伸びるように色々な場所を伸ばしてみてください。
お尻のストレッチ殿筋
 1
1  2
2  3
3
1,2)仰向きに寝ます。
一方のヒザを抱え込み、反対側の肩(左ヒザを抱え込んだ場合は右肩)に向けて引き寄せていきます。
両足を引き付けるのが難しい方は、3)のように片足づつ行ってください。
その際のポイントは反対側のヒザやモモ裏が床から浮かないように注意しながら行います。
 4
4
4)のストレッチは伸ばしている側の肩や胸(写真では左側)が浮いてしまうと、お尻の筋肉が伸びにくくなってしまうため、肩を床に着けるように意識します。
 5
5
5)のストレッチは立てているヒザに、反対の脚を
足首よりも上にかけて胸に引き寄せます。
この時、背中が丸くなってしまわないように真っすぐな姿勢を意識しましょう。
 6
6
6)のストレッチは写真のように足を前後に開いて体を前に倒していきます。
この時も背中が丸くならないように注意してください。
もものストレッチ大腿四頭筋・内転筋
 1
1  2
2  3
3
モモの前(大腿四頭筋)のストレッチです。
両腕を後ろ手につき、一方のヒザを伸ばし、もう一方のヒザを曲げて座ります。(写真1)
両ヒザの間はこぶし1つ分ぐらいの幅にし、開き過ぎないようにします。
その状態からゆっくり体を倒していきます。(写真2)
余裕のある方は肘をつきながらさらに体を倒していきます。(写真3) 出来る方は寝てしまっても構いません。
この時曲げているヒザが床面から浮いたり、両ヒザの間が開かないようにします。
また、腰が反りすぎるのは負荷が高すぎるので、手、肘をついて負荷を緩めてください。
 4
4  5
5  6
6
モモの後ろ側の筋肉のストレッチです。
まずは一方のヒザを伸ばし、もう一方のヒザは曲げて座ります。
伸ばした側のヒザを軽く曲げてつま先をつかんだら、足先の方向に体を倒していきます(写真4)。
この時に腰が曲がらないように注意してください。
つま先は真上か自分の方向に引きつけるとよりストレッチがかかります。
余裕のある人は少しづつヒザを伸ばしていきましょう(写真5)。ふくらはぎまでストレッチされていきます。
柔軟性の高い人はヒザを完全に伸ばして、体をさらに倒していきます(写真6)。
 7
7  8
8
モモの内側のストレッチ です。
両足を広げて体をまっすぐ前に倒していきます(写真7)。つま先は真上に向くようにします。
体が硬い方は片方のヒザを曲げた状態で行っても構いません(写真8)。
どちらの場合も背中が丸くなってしまいやすいので、おへそを前に出すイメージで体を倒しましょう。
もも裏、ふくらはぎのストレッチハムストリングス・下腿三頭筋・アキレス腱
 1
1  2
2
1,2)のストレッチはふくらはぎやももの後ろ側ののストレッチです。
体を正面に真直ぐ向け、写真のように足を前後に開いて少しずつお尻を後ろに引いていきます。
まずはつま先を床につけたままで、出来る方はつま先を上に向けるとさらに伸ばすことが出来ます。
体の柔軟性に合わせて行ってみてください。
 3
3  4
4  5
5
4,5)のストレッチはふくらはぎやアキレス腱のストレッチです。
3)のようにヒザの向きと両足のつま先を同じ方向に向けてください。体は正面に向けましょう。
次に体を前にゆっくりと倒していきます。後ろのかかとが床から浮かないように注意してください。
4)と5)の違いは後ろ足ののヒザが伸びているか曲がっているかです。
ヒザを伸ばしているか曲げているかで異なる筋肉へのアプローチになりますので、両方のパターンを行ってください。
ストレッチのポイント
(1)呼吸について
呼吸は鼻から吸って、口か鼻から吐きます。息を止めず、ゆっくり息を吐きながら行いましょう。
出来るだけリラックスして行ってください。
(2)時間と回数について
一つのストレッチに対して時間は「20秒~30秒」の間を目安に、左右交互に2回ずつ程度行ってください。
「痛い」ところまで無理をして伸ばさず、「気持ち良い」と感じる所まで伸ばすようにします。
筋肉が少しづつ伸びていく感覚がだんだんと得られるようになります。
個人差はありますが、家事や仕事で「少し疲れたな…」という時に行います。
長時間同じ姿勢を続け無ければならない場合なども、合間に休憩を取って軽く身体を動かして頂くと、心身ともに
リフレッシュする事が出来ます。
朝、晩など時間を決めて習慣づけて行うと良いでしょう。

3)姿勢について
より的確に筋肉をストレッチするためには正しい姿勢で行うことが大切です。
それぞれのストレッチのポイントや注意点を参考に正しい姿勢で行いましょう。
また、伸ばしたいと思う筋肉を意識して行うと効果的です。
(4)ストレッチをしない方が良い場合
疲れ具合が大きく痛みが強い場合には無理をせず、ストレッチを中止するか筋肉が少しだけ伸びる程度に抑えます。
「痛み」は体が発する「警告サイン」です。
ストレッチでは対処できず、症状を悪化させることもありますので、まずは治療することをお勧めします。
自重トレーニング自重トレーニングで『カラダ改造』
自重トレーニングで『カラダ改造』

たるんだお腹やお尻が気になって「何とかしたい!」とお悩みなのは、男女かかわらず多いのではないでしょうか?
でも「わざわざジムに通うのも…」と二の足を踏んでいませんか?
カラダを引き締めるトレーニングには何も特別なマシンや時間が必要ではありません。
仕事の合間や入浴前など、ちょっとした時間で、特別な道具を使うことなく行えます。「自重トレーニング」であなたも身体を引き締めてみませんか?
自重トレーニングとは
自重トレーニングとは、自分自身の体重のみで行うトレーニングの事です。
身体を引き締めるためのトレーニングは色々なものがありますが、普段から運動不足気味の方が身体に強い負荷や、負担がかかる様な強度なトレーニングをいきなり行うと、キツい筋肉痛やケガなどを負ってしまう可能性が大きくなり、継続する事も難しくなりがちです。
トレーニング自体も正しいフォームで行わないと、思うような効果が現れなかったり、痛めてしまったりということが起こりますので、まずは正しいフォームを身につけることから始めましょう。
大事なポイントを守って継続すれば、必ず身体は変化し、たるんでいた部分が引き締まるのを実感できると思いますので、興味をもたれた方法から、ぜひ取り組んでみて下さい。

トレーニングの回数と頻度
「筋力をつけたい」「持久力をつけたい」「身体を引き締めたい」など
トレーニングの目的は人それぞれ異なりますし、運動経験(現在運動している、過去にしていた、運動はあまりしたことがないなど)によっても異なりますので、
トレーニングの適切な負荷は皆一様ではありません。
初めてトレーニングをする方、久しぶりにする方は少し筋肉痛が起こることがありますが、その場合はしばらく休養をとり、筋肉痛がなくなったらトレーニングを再開します。
トレーニングを継続することで少しづつ筋肉痛が軽減していき、運動回数も増やすことが出来るようになります。
筋力をつけたい方は、回数15回✕3セットを行います。セット間の休憩は20~30秒ぐらいで良いでしょう。
筋持久力をつけたい方は、回数20~30回✕3セットを行います。休憩は1分ぐらいが良いでしょう。
トレーニングに慣れてきたら、1セットの回数を増やすことより、セット間の休憩時間を短くしてみましょう。
そうすることにより、身体に酸素を多く摂り込むので心肺機能の発達を促進し、筋肥大も起こります。
・正しいフォームで行うためには、反動を使わずにゆっくりと行う ・セット内の休憩時間を長くし過ぎない ・無理をしない。痛みが出た場合はトレーニングを中止する! |
腹筋Shit-up
1)腹圧 :腹筋を行う際に身体が起こせない人や初心者向けの腹筋
・スタートポジション
仰向けになりヒザを立てて寝ます。両手を腰(骨盤)に当てます。
・腹圧を高める
息を吐きながら差し入れた手を腰で床に押し付けるようなイメージで腹部に力を入れ腹圧を高めます。
背中で手を押しつぶした時に腹筋がプルプル震えてくればOKの状態です。


・スタートポジション
ヒザを立てて仰向けに寝ます。アゴを少し引き、両ヒザの間はこぶし1個分開きます
手はモモの上に置きます。
・UP
息を吐きながら肩甲骨が床から離れる程度までゆっくりと体を起こします。
目線はおへそ、顎が上がらない様に注意しながら腹筋を意識しましょう。
ヒザの角度を緩くすると負荷を下げることが出来ます。
・Point
スタートポジションに戻る時はゆっくりとおろしながら、背中が完全に床に着く前に次を行います。
モモに置いた手を頭の後ろ(負荷が強い)、胸の前でクロス(負荷がやや強い)にすると強度が変わります。


・スタートポジション
仰向けの状態になり、股関節・ヒザ関節・足関節を90°に固定し、両ヒザの間はこぶし1個分開きます。
足先は開き過ぎないようにヒザと同じ方向に維持します。
アゴを引き、手の位置は頭の後ろか胸の前でクロスします。(負荷が強い場合は両手をモモの横に伸ばします)
・UP
息を吐きながら肩甲骨が床から離れる程度までゆっくりと体を起こします。
目線はおへそ、顎が上がらない様に注意しながら腹筋を意識しましょう。
・Point
足の各関節の固定が崩れないように90°を保ってください。
スタートポジションに戻る時はゆっくりとおろしながら、背中が完全に床に着く前に次を行います。


・スタートポジション
仰向きに寝ます。お尻と腰の間に手をはさみ骨盤を固定(腰が反りすぎないように)します。
アゴを引き、足関節90°固定、足幅はこぶし1個分開き、両足を床から10cm程度浮かせます。
・UP
息を吐きながら下腹部に腹圧をかけて両足をゆっくり45°ぐらいまで上げていきます。
この時ヒザが曲がったり足先が垂れてしまわないように注意しましょう。
スタートポジションに戻る時はゆっくりとおろしながら、足が床に着く前に次を行います。
背筋Back extension
5)背筋 :脊柱起立筋など背中の筋肉

・スタートポジション
うつぶせになりアゴを引きます。両腕を体の外に開きます。
負荷を強くしたい場合は両腕を前方に伸ばす(バンザイする)と良いでしょう。
・UP
腹圧をかけながら、息を止めずに胸が上がるくらいまで上体を起こします。
腰が痛くなる場合は上体を起こし過ぎなので、反りを少し緩めましょう。
スタートポジションに戻る時はゆっくりおろしながら、床に手や顔が着く前に次を行います。
腕立伏せPush-up

腕立伏せの際の手の位置と幅:手の位置や幅で効かせたい筋肉や運動負荷が変わります(写真はver.2)。
床にうつぶせになり、体幹に沿わせてバストトップの高さに手をつきます。
ver.1 :手幅(体幹のすぐ横につく)・・・主に上腕のトレーニング
ver.2 :手幅(体幹より手の平1つ分、左右外側につく)・・・胸、肩、上腕のトレーニング
ver.3 :手幅(体幹より手の平2つ分、左右外側につく)・・・主に大胸筋のトレーニング


・スタートポジション
頭から背中、かかとまでが一直線になるようにポジションととります。(腹圧を少しかけます)
目線はまっすぐ(✕:下を向く、アゴが上がる)のまま、肩甲骨を寄せながら、肘を曲げていきます。
・プッシュ時
目線、手の位置を変えずに、肩甲骨を寄せたまま腹圧を維持しながら(✕:腰を反らる、腰を丸める)、肘を伸ばし ていき、ゆっくりとスタートポジションに戻ります。


床で行う腕立て伏せのうち、負荷が軽いバージョンです。
こどもや女性の方で、下記の「 3)ヒザをつかずに行う」が難しい場合はヒザをついてやってみましょう。
腰が反り過ぎたり、お尻が上がったりせずに、体が一直線になるようにコントロールしてください。


頭、背中、腰、お尻、かかとが一直線になるようにコントロールしながら上下します。
手の平の位置がちょうど肩の真下に、かかとの位置はつま先よりも上(頭側)に来るようにします。
疲れてくると頭が垂れたり、アゴが上がってきますので頭の位置が動かないように意識して行います。
3)の腕立伏せが出来た方は、スタートポジションでの手幅を広くしたり、狭くして行ってみてください。
スクワットSquat
スクワットトレーニングは下半身、特にお尻やモモ周りを鍛えるのに有効なトレーニングです。
脚を細く引き締めたい女性や、脚力の低下が気になる高齢者にもおすすめです。
また、走る競技やジャンプ競技など下半身のパワー発揮が必要な競技にも欠かせない重要なトレーニングです。


足幅を肩幅と同じか、少し広めに開きます(股関節が硬い方は開いた方が楽です)。
足先(第二指)と膝の方向を同じにし、手はバランスをとるために前に伸ばして両手を重ねます。
目線は正面に向け、アゴを少し引いてください。
腹筋を意識し、腰が反りすぎたり、背中が丸く猫背にならないように注意します。
・ダウン時


お尻を後ろに引くようにしながら、ゆっくりと股関節を曲げていきます。
ヒザの位置はつま先の真上か少し前までにし、つま先よりも前に出過ぎないように注意します。
頭から背中、腰、お尻をつなぐラインが一直線になるようにします(腰が反り過ぎたり丸まらないように)。
モモと床面が平行になるぐらいまで股関節を曲げていきます。(腰が丸くなる場合はそこまで曲げなくてOK)
足の裏全体(慣れるまではカカトを意識)で床を踏んでいることを感じながら、ゆっくりとスタートポジションに戻ります。
鏡を見ながらヒザの位置や腰の反り具合など、正しいフォームがとれているかを確認するといいでしょう。
ランジLunge
ランジは、体幹、下半身の筋力を鍛えることに加え、バランスコントロールを得るのにも最適なトレーニングです。
走る、切り返す、投げるなどの動作で重要になる股関節の動きをバランスを取りながら行うことで、より競技動作に近いかたちで練習することが出来ます。
ここでは前方に踏み出すフォワードランジをお伝えしていますが、その他、横方向(サイドランジ)や後ろ方向(バックランジ)のトレーニングなどもありますので、必要に応じて取り入れてみてください。


背中を真っすぐにして立ち、腹圧を高めます。目線は正面に向け、手は顔の高さに上げてキープします。
・ダウン時

背中は真っすぐ、目線も正面に向けたまま、足幅は股関節の幅、股関節と膝関節が一直線(床と平行)になるように、体の前に一歩踏み出します。
前に出した足は、股関節90°、ヒザ関節90°に曲げ、足関節がヒザの下に来るように足全体で接地します。
後ろの足はヒザ関節90°で体の下にくるように曲げます。その際にヒザは地面につかないようにし、カカトは浮かせます。
スタートポジションに戻る時は前に出した足のカカトで床を強く蹴って戻り、次は左右の足を変えて行います。
注意ポイントは、前足のヒザが内側に入りやすいので真っすぐに向けることと、骨盤が回転しやすいので左右の股関節をつな
いだ面が正面を向くようにすることです。
また、前に一歩踏み出した時やスタートポジションに戻る時に、腹圧が抜けてお腹が伸びてしまったり、逆に体が前に倒れ込んでしまいやすいので、体幹のコントロールもしっかりと行ってください。